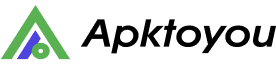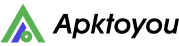近年、中国人観光客の間で「日本のニッチな観光地に行きたい」という傾向が強まっている。日本の観光地といえば、やはり有名な場所が多く、その人混みや混雑が問題となることも少なくない。しかし、最近では、地元民しか行かないような穴場や裏道、スナックなど、観光地ではない場所を訪れる中国人観光客が増えている。これらの場所は、SNSで「小紅書」(中国版インスタグラム)などで紹介されると、瞬く間に注目され、多くの観光客が殺到する。
例えば、富士山が見渡せる新倉山浅間公園の人気スポットは、駐車場を有料化するなど、来場者の多さが問題となっている。これもSNSで「映えスポット」として広まり、特に中国人観光客の間で急増している。彼らは、小紅書で見つけた情報に従って観光地を訪れ、その影響力は非常に大きい。
一方、中国国内でも観光地はすでにオーバーツーリズムに悩まされているが、広大な土地を有するため、観光客を受け入れるキャパシティにはまだ余裕がある。しかし、日本の観光地は道幅が狭く、街づくりもコンパクトで、観光地と住宅地が隣接していることが多い。このため、観光客が一度に集中すると、すぐに混雑してしまい、特に都心部ではそれが顕著だ。
最近、日本の観光地に多く訪れる外国人観光客の増加が問題となっており、特に中国からの観光客が増加することで、観光地のキャパシティが限界を迎えている。たとえば、東京の浅草や渋谷、新宿などでは、街が密集しており、店舗も小さく、座席と座席の間隔が狭いため、感染症の拡大が速く進んでしまうこともある。
このような状況に対応するためには、観光地や店舗に対して規制を設ける必要が出てきている。観光税や入場料の導入、二重価格制度や罰金制度の導入などが検討される中、どうしても一定の制限が必要であると感じる声も強い。観光地の管理と規制のバランスをどう取るかが、今後の大きな課題となるだろう。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement