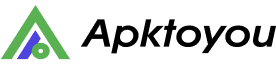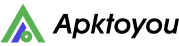デジタル終活がますます注目される中で、特に重要なのは故人のスマホの取り扱いです。スマホに保存されたデジタル財産や契約情報にアクセスできないことが遺族にとって大きな損失を招く可能性があります。2025年2月、独立行政法人国民生活センターは「デジタル終活」の重要性を訴え、トラブル防止策を示しましたが、その中心にあるのはスマホです。
スマホ決済サービスの損失額
故人のスマホが開けない場合、まず問題となるのはスマホ決済サービスに残ったチャージ残高です。日本ではQRコード決済サービスが広く使われており、平均的な月末の残高は約7700円です。さらに、複数の決済サービスを使っている人が多く、1台のスマホには約1万2000円の残高があると計算されます。故人のスマホに残された決済サービスの残高は、財布に残された現金と同じような役割を果たしているため、アクセスできないことは大きな損失です。
預金口座の損失
スマホを通じて銀行口座の情報が得られない場合、隠れた口座を見つけることが難しくなります。2023年の調査によると、3つ以上の口座を持っている人が多く、1口座あたりの平均残高は約2万2000円です。もし未発見の口座があれば、その残高が埋もれたままとなり、4万4000円の損失となる可能性もあります。
ロック解除の難しさと費用
スマホのロック解除は非常に困難で、外部の専門業者に依頼する場合、成功報酬ベースで30万円の費用がかかることもあります。解除できる保証はなく、依頼しても中身にアクセスできない場合もあります。
総損失額の試算
これらの損失を合計すると、約5万円となります。しかし、これはあくまで決済サービスや預金口座などに限定した場合であり、サブスクの支払い義務や、スマホ内の他のデジタル財産の価値を考慮すると、損失額はさらに増える可能性があります。
デジタル終活を行い、スマホの管理方法を事前に決めておくことは、遺族がスムーズに相続手続きを行うために非常に重要です。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement