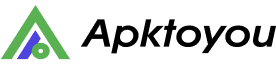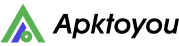退職所得に対する税制優遇措置が取られている背景には、退職金が長年の勤務に対する報酬であり、また老後の生活資金として重要な役割を果たすからです。このような税制上の配慮は、他の所得と合算して課税されると、その年の所得額が急激に増え、納税額も不適切に増加することを防ぐためのものでもあります。税理士で「不公平な税制をただす会」の共同代表を務める浦野広明氏は、こうした措置が退職金を受け取る人々にとっての公平性を保つために重要であると解説しています。
しかし、退職金に対する税制優遇措置の見直しが検討されている背景には、近年の労働市場の変化があります。転職が一般的になり、長期間同じ企業で働くことが少なくなったことが影響しています。また、成長分野への労働移動を円滑にするために、退職金に対する優遇措置を見直す動きが高まっています。
現行の退職金課税では、「2分の1課税」という仕組みが採用されています。これは、退職金に対して一定額の控除を行い、その後残った額に税金が課せられるというもので、特に長年勤務した人々にとっては大きな恩恵となっています。例えば、勤続20年以上の勤務者が退職金として2000万円を受け取る場合、退職所得控除が適用されるため、実質的な課税額はゼロとなります。しかし、この「2分の1課税」の撤廃が議論されており、もしこれが実施されると、退職金全額に課税されることになり、大きな増税につながる可能性があります。
実際にシミュレーションを行った場合、勤続38年で2000万円の退職金を受け取ると、現行制度では退職所得控除額が2060万円となり、納税額はゼロです。しかし、見直し後の制度では、退職所得控除額が1520万円に縮小され、課税対象となる額は480万円となります。この場合、所得税が53万2500円、住民税が48万円となり、合計で101万2500円の増税が発生することになります。
仮に「2分の1課税」が残されたとしても、増税額は約40万円となり、退職後に受け取る退職金の額に対して負担が増えることになります。実際に見直しが実行される際には、「激変緩和措置」が検討される見込みですが、退職者にとってはこれらの変化は避けがたい負担増となる可能性が高いといえます。
退職金課税の見直しが進む中、今後どのような制度変更がなされるのか、注目が集まっています。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement