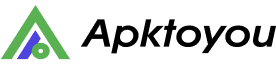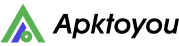トランプ政権による輸入自動車への25%関税発動は、日本の自動車業界に大きな波紋を広げた。特に日産自動車にとっては、ホンダとの経営統合交渉が破談となった今、今後の経営戦略が注目されている。
早稲田大学ビジネススクール教授・長内厚氏によれば、現時点で最も現実的なシナリオは「日産が独自に経営を立て直す」ことだという。具体的には、業績不振に陥ったアメリカと中国という主要市場での立て直しが最優先課題だ。
中国では現地メーカーの台頭によりEVのみでは競争力が不足し、アメリカではEV化の反動として内燃機関車の需要が再び高まっている。特に中西部では石炭火力による電力が主流であり、EVより内燃機関車の方が環境負荷が低いとする試算もある。この状況下では、日産が持つe-POWERなどのハイブリッド技術の強化がカギとなる。
一方で、再びホンダとの提携交渉に乗り出す可能性も否定できない。特にEVやハイブリッドの技術協業、もしくはホンダのシステムをOEMとして日産ブランドで販売する形式など、柔軟な連携の道が考えられている。これは、海外企業との提携よりも現実的でリスクの少ない選択肢だ。
海外企業として名前が挙がるのは台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業である。同社CSOで元日産の関潤氏は「日産とは親和性がある」と発言しており、注目を集めている。ただし、政府が国内技術流出を懸念する可能性もあり、全面的な提携には慎重さが求められるだろう。今のところは、三菱自動車がEV生産を一部委託しているような限定的提携が現実的とされている。
長内氏は「中途半端な規模のメーカーはEVシフト時代には生き残りが難しくなる」と指摘し、今後は企業の統合に限らず、ブランド間でプラットフォームや技術を共有する方向が加速する可能性を示唆している。
現在の日産社長は商品企画部門出身で「車好き」な一方、自身の好みと市場ニーズを冷静に区別できるかどうかが経営手腕のカギになるという。
当面は独力再建が続くだろうが、成果次第では再び他社との提携が浮上する可能性がある。業界全体が大きな転換点に差しかかる中、日産の今後の一手に注目が集まっている。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement