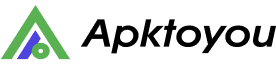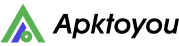鹿児島市内でもバス運転手の不足が深刻化しており、路線バスの減便や廃止が相次いでいます。特に地方の自治体では住民の移動を支えるためのバス運行が困難となり、求人の難しさも増しています。運転手不足の背景には、変則勤務や事故のリスク、さらには高い平均年齢などが影響しています。バス業界は、将来的にさらに深刻な人手不足に直面する可能性があり、2030年度には3万6千人の運転手が足りなくなるとの試算もあります。
この問題に対して、政府は2024年3月に外国人労働者を受け入れるため、バス運転手などの自動車運送業を「特定技能」在留資格に追加しました。これにより、外国人がバス運転手として働く道が開けることになり、9月からは20言語で学科試験を受けることができるようになりました。
例えば、ベトナム出身のグェン・ヴァン・ナムさん(35歳)は、鹿児島で通訳として働く傍ら、日本の大型免許を取得しようとしています。ナムさんは、自国で取得した免許を日本の普通免許に切り替えた経験を活かし、大型免許の取得を目指しています。しかし、外国人が日本で免許を取得する際には、実技の講習や日本語の壁が立ちはだかることもあります。特に、実技講習では、言語のニュアンスや臨機応変な対応が難しく、時には重大な事故につながる恐れもあります。
また、バス運転手になるためには、日本語能力試験で「N3」以上の合格が求められますが、一部業界関係者は「N4でも十分ではないか」と指摘しています。運転技術を重視すれば、言語能力のハードルを下げても問題はないという意見もあります。
さらに、外国人労働者を採用する際には、送り出し機関への手数料などが発生するため、事業者側の負担が大きいのも現実です。鹿児島交通の西村将男副社長は、「外国人材がバス業界に必要だが、実際に集まるかどうかは疑問」と話し、現場の課題に対する理解を政府に求めています。
外国人労働者がバス業界の課題解決のカギとなるには、今後の制度改善や支援が不可欠であり、その道のりはまだ遠いと感じている関係者も少なくありません。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement