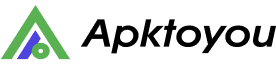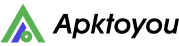日本銀行の植田和男総裁は26日、生鮮食品を中心とする食料品価格の上昇が家計に与える影響について強い懸念を示した。消費者物価指数(CPI)が前年比2%を超える水準で推移している現状を「国民生活に深刻な影響を与えている」と認め、この傾向が一時的なものではない可能性にも言及した。
「特に購入頻度の高い食品類の値上がりは、消費者の物価上昇期待を変化させるリスクがある」と指摘。日銀としてはこうした要素も考慮しながら適切な金融政策運営を行う方針を明らかにした。
今年1月に17年ぶりとなる政策金利引き上げ(0.5%程度)を実施した日銀は、経済・物価情勢を見極めつつ段階的な金融緩和調整を継続する構えだ。市場関係者の注目は次回利上げ時期(7月との観測が優勢)とそのペースに集まっている。
注目されるのは総裁の発言内容だ。従来、日銀が物価見通しを作成する際には変動要因となる生鮮食品を除いたコア指数を重視してきたが、「今後は生鮮食品を含めた包括的な物価動向も注視していく」との新たなスタンスを示した。
総務省発表によると、2023年12月の全国CPIは前年比3.6%上昇(生鮮食品除くコアCPIは3.0%)。特に生鮮食品17.3%という急騰ぶりが全体指数を押し上げる形となった。この数値は2023年1月以来の高水準で、食料品全般(生鮮除く)でも4.4%の上昇が見られた。
記者会見では利上げ幅に関する質問に対し、「0.25ポイントという小幅調整には合理性があった」と評価しつつ、「今後の金利操作幅については経済・物価情勢に応じて柔軟に対応する」と述べた。これは市場予想通り7月にも追加利上げを行う可能性を示唆するものと受け止められている。
国際情勢に関しては米国政治への言及があり、「トランプ政権時代の方針変更が世界経済へ与えた影響から学ぶべき点が多い」と指摘。「今後の米国政策動向を見極めながら自らの経済見通しに反映させていく」との考え方を示した。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement