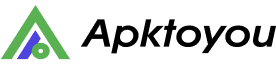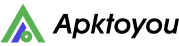「全世代型社会保障」という言葉、ニュースなどでよく耳にするようになりましたが、実際に得をするのは誰で、損をするのは誰なのでしょうか? とくに子どものいない共働き世帯(DINKs)にとっては、その影響が気になるところです。今回は、制度の基本構造や家計への影響をわかりやすく解説します。
建前は「支え合い」、本音は「維持が限界」
政府が目指す「全世代型社会保障」とは、高齢者だけでなく、すべての世代が支え合う仕組みです。従来のように「現役世代が高齢者を支える」モデルでは、少子高齢化社会に対応できなくなったため、新たな制度設計が必要とされているのです。
この制度は、年金や医療、介護といった社会保障だけでなく、ひとり親支援、8050問題、ヤングケアラー、孤立問題など、さまざまな社会課題にも対応しようとしています。つまり、社会全体の福祉を再構築するための大きな改革だと言えるでしょう。
応能負担とは? 負担は「能力」に応じて
「全世代型社会保障」のもう一つの柱が、「応能負担」という考え方です。これは、収入や資産などの「支払える能力」に応じて負担額を決める仕組みです。
たとえば、高額療養費の自己負担限度額を高所得者だけ引き上げる案や、株式譲渡益・配当にかかる金融所得課税の強化などがこの考え方に基づいています。
つまり、「稼げる人や資産を多く持つ人には、より多くの負担をお願いする」ということ。特にDINKsや資産家のように相対的に負担能力が高いとされる層は、今後より強くターゲットにされる可能性があります。
マイナンバーと資産課税の連動も視野に?
さらに、マイナンバーカードと銀行口座の紐づけが可能になったことで、国が個人の金融資産を把握しやすくなっています。これは、将来的な資産課税強化の布石ではないかとも言われています。
「見える化」された資産に対し、税をかけることで社会保障の財源を確保しようという狙いがあるのかもしれません。これもまた、全世代型社会保障の「影の顔」といえるでしょう。
DINKs世帯の家計への影響とは?
こうした改革が進むなか、DINKsのような子どもを持たない共働き世帯は、恩恵を受けにくい反面、負担ばかりが増える恐れがあります。子育て支援や教育費の補助といった給付の恩恵を受けず、税や社会保険料の負担だけが増す「損な立場」になりかねないのです。
人生100年時代、必要なのは「戦略的な家計管理」
図表にもあるように、私たちの人生には収入が多い時期と少ない時期、支援を受ける時期と支える時期があります。全世代型社会保障のもとで人生を設計するには、自分がどの時期にどれだけ負担し、どれだけ恩恵を受けられるのかを冷静に見極めることが重要です。
まとめ:支え合いの美名のもとに広がる格差
「全世代型社会保障」は、表面的には「みんなが助け合う制度」ですが、実際は支える側と支えられる側のバランスが問われる制度です。とくにDINKsや資産保有者にとっては、家計への影響が大きくなる可能性があるため、冷静な分析と対策が求められます。
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement